学生小説家たちの物語、それが「小説の神様」である。
作品情報
本作は2016年に書き下ろしで文庫として出版されました。
相沢さんのことを名前から女性だと勘違いしていたのですが、調べたら男性でした。すみません。
ちなみに「小説の神様」はコミカライズ化されています
さらに実写映画も2020年10月2日に公開予定です。

あらすじ
高校生で作家デビューしたものの作品が売れない主人公 “千谷 一也” が、同い年で美しい容姿を持ち、同じく作家である “小余綾 詩凪” と出会う。果たして彼らの出会いが生み出すものとは。
感想
みなさんは小説を読みますか?
私は結構読みます。小学生、中学生のとき月に一冊小説を買ってくれるという、ご褒美的なものがあったので、その影響ですかね。
まあ弟は読書家ではないんですが。
高校生くらいまでは、自分の中での本の良し悪しの基準はストーリーでした。
読んでいる最中に、自分で展開の予想を3、4つくらい立てて、それとは異なる結末を迎えた作品はかなり印象に残りました。
ただ最近はその基準が少し変わってきています。
単純にストーリーだけで判断するのではなく、登場人物(特に主人公)に感情移入できるか、作品が何を伝えたいのか、場面に応じた言葉の選び方、などいろいろな観点から作品を俯瞰するようになっています。
さて本作「小説の神様」は、小説の作り手たちの物語です。
私たちは小説を読む側なので、彼らが何を伝えたかったのか、それを掴むには作品から得るしかありません。
小説家が紡いだ小説家の物語。それを読むことで、彼らがどのような思いで執筆に挑んでいるのかを知る手掛かりになるのではないでしょうか。
そしてそれを深く知るためには、ストーリーだけでなく言葉選びや情景描写、キャラクター設定など多くの視点から作品を読む必要があります。
そういう意味でいうと、最近いろいろな観点から読書できるようになったことは、一冊の本から汲み取るものが増えたのでいいことなのではないでしょうか。
自分でいうのも、おこがましいんですけどね。
クリエイターは自分が伝えたいことを作品として形にする。この作品を読む前は、それが普通で当たり前なことと思っていました。
しかし実際にはクリエイターにも生活があり、人によっては家族があり、お金を稼いで食べていかなくてはなりません。
そうなってくると自分の作りたい作品と、消費者である読み手が求める作品が合致しないこともあり、そこに葛藤を感じてしまうこともあるのだと気づかされました。
高校生ぐらいの年だと、現実を現実として受け入れたくない部分があるので、この葛藤が表に出やすく描きやすいのかなと感じます。
大人になってくるとリアリスティックになってきて、受け入れざるを得なくなるので。
さて、本作は実写映画も来月(10月2日)公開予定です。小説の世界観を映像でどう表現するのか、映画も合わせて確認してみてはいかがでしょうか。
今回はここまで
最後まで読んでいただきありがとうございます。
じゃあね
※アイキャッチの書影画像は版元ドットコムから利用しています

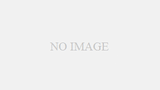
コメント